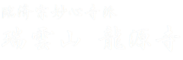歴史・人物
龍源寺の歴史、およびゆかりの人物をご紹介致します。
(画像をクリックすると拡大表示されます)
歴 史
龍源寺は山号を「瑞雲山」といい、臨済宗妙心寺派※の禅寺であります。
室町時代に、伊勢国三重郡川尻城(現在の四日市市河原田)の城主が山門諸堂を建立し、妙心寺第三十世 江南殊栄禅師を請して禅の修行道場としました。
そして江戸時代初期、妙心寺第百七十五世・絶江紹是禅師によって再興されました後、江戸中期に至りますと、臨済宗中興の祖・白隠禅師と、その高足(弟子)である東嶺禅師が滞在して禅を説かれました。
龍源寺は創建以後、寺領百石を所領していましたが、明治期の廃仏毀釈※および太平洋戦争後の農地解放により、その寺有財産をことごとく失くしました。
明治以前までは、格式高い寺として檀家も僅かしか持たない寺でしたので、維持管理は大変困難を極めました。
さらに住職の居ない時もありましたが、檀信徒の篤い協力・尽力・信仰心に支えられて、現在まで連綿と法灯を受け継ぎ、開創より八百年余の歴史を有しています。
※廃仏毀釈・・・明治政府の神仏分離政策から波及して発生した、民間の廃仏運動。
※臨済宗妙心寺派について(クリックで表示)
- 臨済宗
お釈迦さまより28代目 達磨大師が西暦520年頃、インドより中国に渡り「禅」を広められ、以来中国では「北宗禅」と「南宗禅」に分かれ、さらに五家七宗へと分かれました。
この内、日本に伝わっているのは、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗です。
臨済宗は栄西、曹洞宗は道元によってそれぞれ鎌倉時代初頭に、黄檗宗は中国僧・隠元により、江戸時代初頭に日本へと伝えられております。
その後臨済宗は、鎌倉幕府の庇護のもとで上級武士僧へと広まり、曹洞宗は一般民衆に広ってまいりました。臨済禅は、日本の文化史上に多くの影響を与えました。
それが禅文化(建築・庭園・食物・芸術・儀礼・武道)です。- 禅文化の例
建築:書院造り(金閣寺、銀閣寺)
庭園:枯山水庭園(天龍寺)
食物:精進料理
芸術:墨蹟(禅僧の書)、水墨画、茶道、華道
儀礼:小笠原流礼法
武道:無刀流(山岡鉄舟)
- 禅文化の例
- 妙心寺派
臨済宗は現在14の派に別れ、それぞれが本山を有しています。
これらは、鎌倉から室町時代に至るまでの期間に、中国の南宋の五山制度を模して、鎌倉・京都五山が定められ、それぞれの下に十刹の寺が定められた五山十刹制度の変遷を経たものでございます。- 妙心寺
建武4年(1337年)、花園天皇の勅願によって無相大師を開山(開創者)として創建されました。
末寺は全国に3,400ヶ寺を数えます。
妙心寺には搭頭46ケ寺があり、10万坪の境内には七堂伽藍の建物が並び、多くの重要文化財や史跡・名勝指定の庭園、寺宝が保管されています。
- 妙心寺
写真提供:https://www.myoshinji.or.jp/(妙心寺ホームページ)
ゆ か り の 人 物
 江南殊栄禅師
江南殊栄禅師
 絶江紹隄禅師
絶江紹隄禅師
 白隠禅師
白隠禅師
駿河国原宿長沢家の三男として貞享2年(1685)に生まれ、名を岩次郎といった。
15歳の時、原の松陰寺で出家され、慧鶴と名づけられた。
19歳より旅に出て諸国を修行。五百年間に一人と言われるほどの高僧となり、後に[日本臨済宗中興の祖]と仰がれるようになった。そして、全国諸寺で積極的に禅の講義を行う。
坐禅とは縁遠い一般大衆に向けた啓蒙にも積極的で、書画をよく描き、和文の坐禅和賛・仮名法語を著すなど、禅の普及に努めた。
著書は多数ある。それらは、難解な漢文語録と仮名法語に分かれる。
- 語録 : 「毒語心経」「槐安国語」等
- 仮名法語 : 健康法を説いた「夜船閑話」等
また「駿河には過ぎたるものが二つあり 富士のお山に原の白隠」とも歌われた。
明和5年(1768)84歳で遷化、御桜町天皇より神機独妙禅師を、明治天皇からは正宗国師の諡号を賜った。
近江国神崎で享保6年(1721)に生まれ、9歳の時に神崎の大徳寺で出家、17歳より行脚の旅に出る。
23歳の2月、ここ龍源寺での修行後、駿河の白隠禅師に師事する。
一時、病をえて白隠のもとを離れたが再び帰り、29歳で白隠禅師より嗣法する。その時、白隠をして「我が弟子百人を超えるが、東嶺に優る者なし」と賛嘆せしめた。
この後、白隠の諸国教化に随侍して布教を助ける。
白隠の死後、師匠と同様に諸寺の求めに応じ、禅の布教に努める。
著書には禅修業の手引き「宗門無尽燈論」をはじめ「白隠禅師年譜」等など多数ある。
書画も白隠に劣らず大胆で、独創的な世界を形成している。
寛政4年(1792年) 72歳で遷化、朝廷より仏護神照禅師の諡号を賜わる。
 平敦盛
平敦盛
平安時代末期の武士で平経盛の子。
寿永3年(1184)、源平一ノ谷の戦いで熊谷直実によって討たれる。
平家物語において敦盛が直実に討たれるその場面は有名であり、謡曲「敦盛」の題材にもなった。
横笛の名手として知られており、討たれた時も「小枝の笛(青葉の笛)」を所持していた。
青葉の笛(小枝の笛)
敦盛の祖父・忠盛が鳥羽院から拝領した名笛(めいてき)。
現在、神戸の須磨寺に宝物としてつたえられている。
 有山主馬助
有山主馬助
南北朝時代には有田氏が川後(川尻)城を築き、信長の北伊勢侵攻までこの地で統治していた。
「北畠暦記」「伊勢国太平記」に北畠家臣として記す。
「姓氏家系大辞典」によると伊勢の有山氏・有山主馬助は三重郡川尻城主で、永禄11年(1568)に信長の為に亡ぼされたとされている。